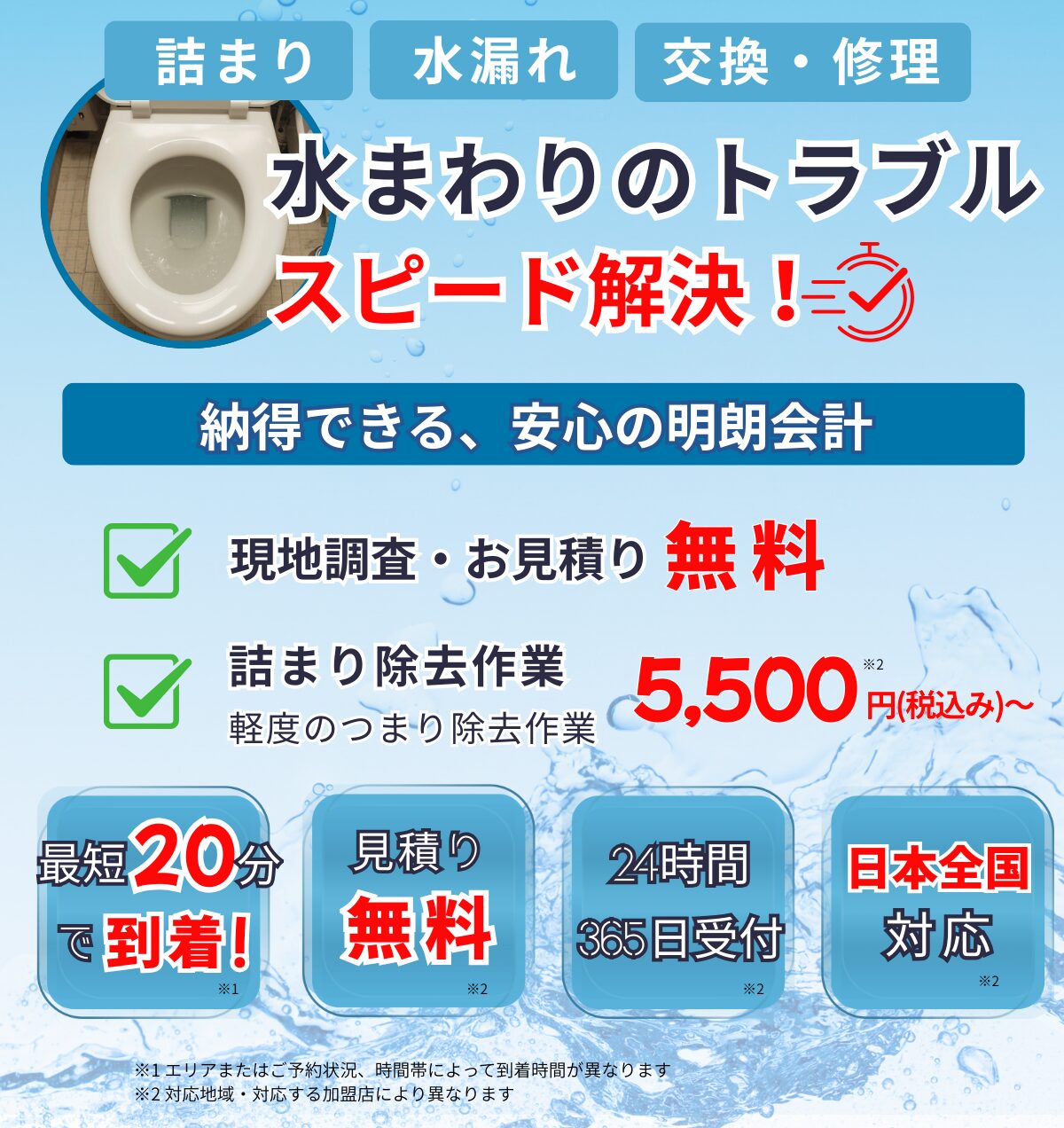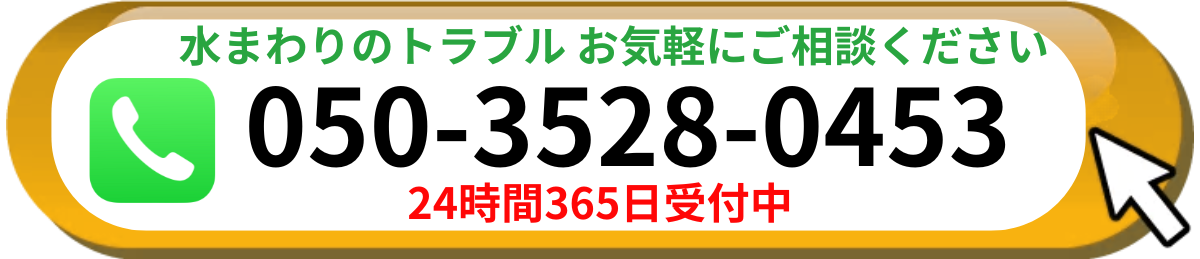トイレに流せるシートには掃除用以外にもさまざまな種類がありますが、いずれもゴミを室内に持ち込む必要がなく、衛生的で人気があります。しかし、商品によっては便器や排水管に詰まることがあるようです。
そこで本記事では、流せるシートの仕組みとメリット・デメリット、詰まるケースを詳しく解説します。後半では詰まらせることなく上手に使う方法や商品の選び方も解説するので、ぜひ参考にしてください。
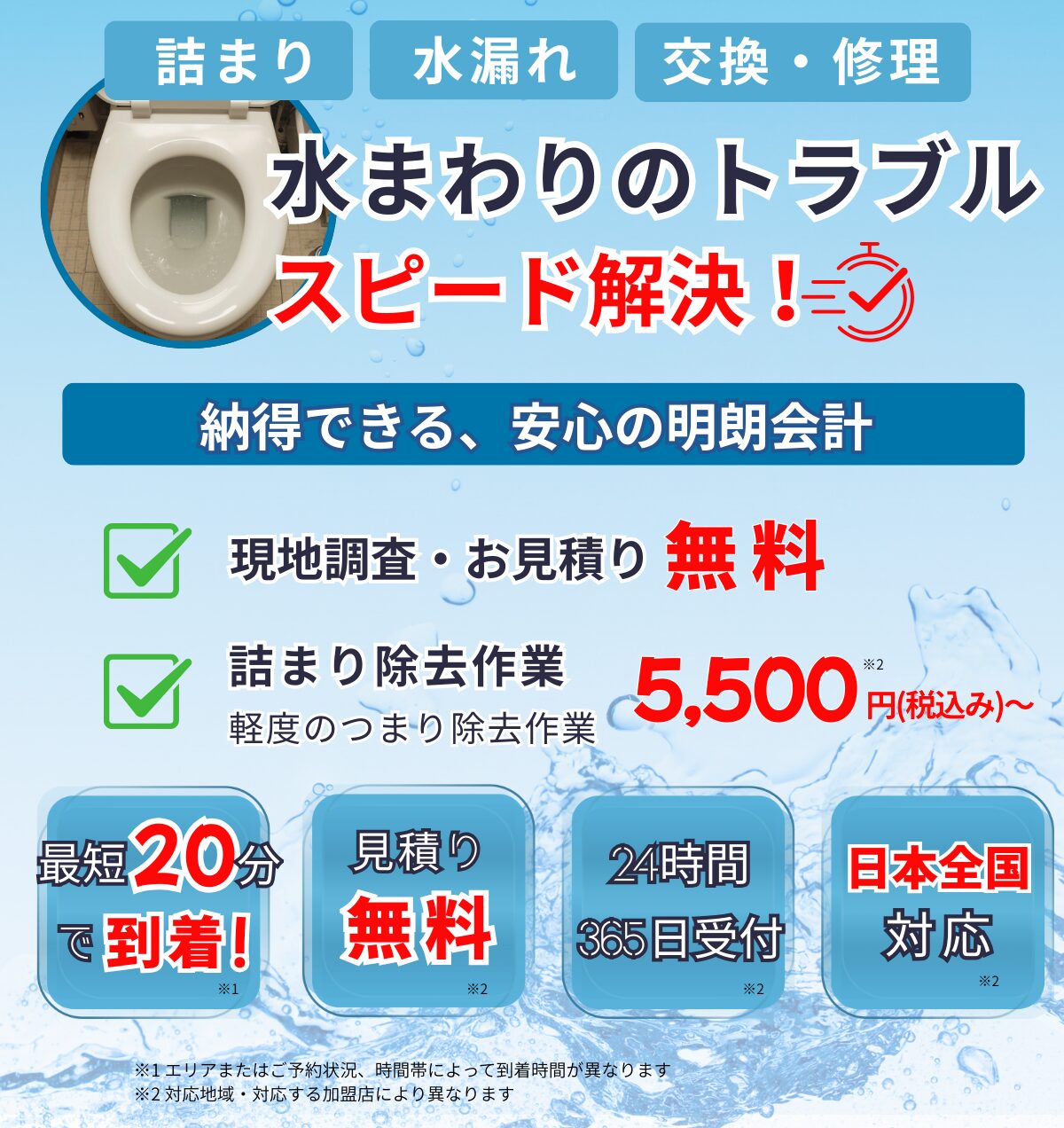
目次
トイレの流せるシートとは?

トイレの流せるシートは、使った後にそのまま便器に流して処分できるアイテムです。まずは、トイレの流せるシートの種類となぜトイレに流せるのか、理由を解説します。
流せるシートの種類
トイレの流せるシートは、主に次の3種類に分類されます。
トイレに流せるシートの種類
- 掃除用シート
- おりものシート
- 便座シート
掃除用シートはウェットティッシュのような見た目で、トイレの拭き上げ掃除に使うためのものです。便器だけでなく床や壁の掃除にも使える厚手のタイプもあります。掃除後は便器に流すだけなので衛生的です。
また、従来はゴミ箱に捨てるしかなかったおりものシートでも、トイレに流せるタイプが登場しています。
流せる便座シートは、90年代の商業ビルではメジャーでした。節水型トイレの登場やペーパーレスの観点から多くの場所で姿を消しましたが、コロナ禍以降で再注目されている商品です。空港や観光地、介護の現場などでは現在も活用されるケースがあります。
なお、本記事の「トイレの流せるシートのメリット」以降では、掃除用のシートをメインに解説します。
トイレに流せる仕組み
トイレの流せるシートは、トイレットペーパーのように水でほぐれる繊維で作られています。便器内の強い水流にさらされると繊維同士の結びつきが緩み、バラバラに分解される構造です。
水流によってほぐれるため、水滴や摩擦で簡単にで破れることはありません。
トイレの流せるシートのメリット

ここからは、掃除用の流せるシートについて解説します。主なメリットは次のとおりです。
流せるシートのメリット
- 汚れたシートを室内に持ち込まずに済む
- ゴミを減らせる
- トイレのすみずみまで掃除できる
汚れを拭き取ったシートはそのままトイレに流して処分できます。ゴミ箱に捨てる必要がないため、室内に汚物を持ち込む必要がありません。ゴミのニオイやゴミ箱内のかさばりを気にせずに使用できます。
また、流せるシートだけでトイレ全体を掃除できることもメリットです。便座や便器のフチ、壁、床、ドアノブ、ノズルなどさまざまな場所に使えます。衛生面と掃除の手間を軽減できる、利便性に優れたアイテムです。
トイレの流せるシートのデメリット
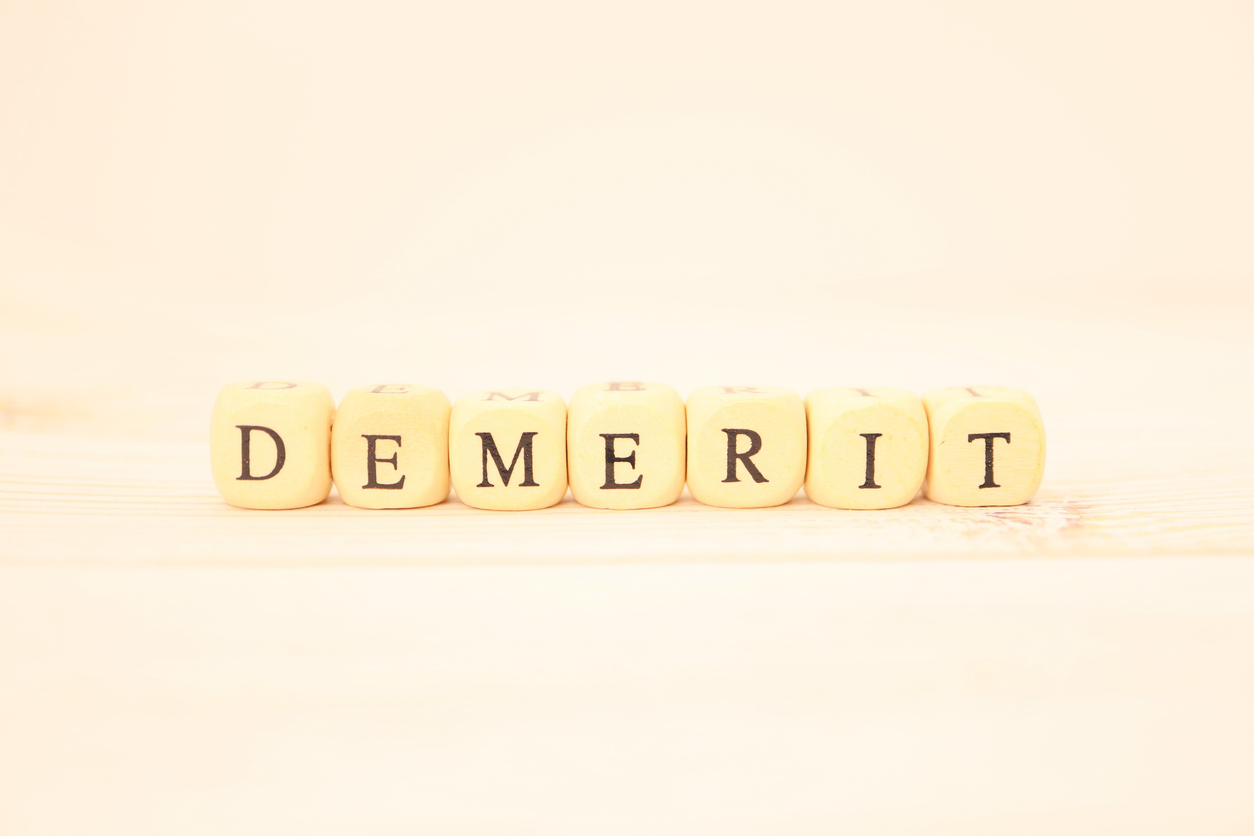
トイレの流せるシートには、次のような注意点もあります。
流せるシート注意点
- 破れやすい
- 詰まることがある
水に溶ける構造のシートとはいえ、掃除中に簡単に破れるようなことはありません。しかし、ゴミ箱に捨てるタイプの掃除シートよりは破れやすいつくりです。
製品によって強度に差があるため、このデメリットを強く感じることもあるでしょう。
また、流せるシートとはいえ、場合によってはトイレ詰まりの原因となることもあります。特に節水トイレでの使用や一度に大量に流すような使い方には注意が必要です。流せるシートと詰まりの関係については、次の章で詳しく解説します。
流せるシートなのに詰まることがある?

「トイレに流せる」と記載されたシートでも、使い方や製品によってはトイレの詰まりを引き起こすことがあります。主な4つの原因を解説します。
節水トイレとは相性が悪い
節水性能が高い「節水トイレ」は、流せるシートとの相性がよくありません。
一度の洗浄で使用する水の量は、従来のトイレでは13~15リットルが平均でしたが、節水トイレでは4~6リットルです。一般的なトイレットペーパーであれば問題なく流せるように設計されていますが、流せるシートは想定されていません。
TOTOの公式サイトでも流せるシートについて、次のように注意喚起しています。
注意喚起
≪対象商品≫
ベッドサイド水洗トイレ:EWRS320系・EWRS310系
トイレットペーパー以外のものは流してはいけません。
トイレに流せる、とうたわれている紙でも、トイレットペーパーと同等の性能がない場合があり、故障の原因になることがあります。
引用
対象となっているEWRS320系・EWRS310系は節水トイレです。節水トイレにシートを流してはいけないということではありませんが、ゴミ箱に捨てることを推奨するメーカーもあるようです。
最近のトイレはほとんどが節水トイレのため、流せるシートを使う際は注意が必要です。
浄化槽タイプのトイレでは推奨されていない
し尿や生活排水を微生物で分解し処理する「浄化槽タイプ」のトイレは注意しましょう。
トイレに流せるシートといっても、トイレットペーパーよりは水に溶けにくい構造です。そのため、シートの溶け残りが浄化槽内の「ろ材(微生物が付着する部品)」の周囲に張り付いてしまう可能性があります。
結果、ろ材への微生物の付着量が減少し、浄化槽の処理性能も低下する恐れがあります。
シートの性能が低いことがある
トイレの流せるシートには、規格がありません。そのため、商品によって詰まりやすさのリスクが変わります。
トイレットペーパーには日本産業規格(JIS P4501、JIS規格)があり、一般的なトイレットペーパーはこの規格の基準を満たしています。しかし、流せるシート用の規格は存在しないため、JIS規格の基準で流せるシートを作るかどうかはメーカーの判断次第です。
つまり、すべての流せるシートがトイレットペーパーと同等の流しやすさ・ほぐれやすさが担保されているとは限らないということです。JIS規格の基準を満たさない流れるシートの場合、詰まりの原因となる可能性があります。
JIS適合かどうかは「トイレの流せるシートの選び方」で詳しく解説します。
配管の構造と相性が悪い
排水管の構造によっては流せるシートが途中でひっかかり、詰まりの原因になることがあります。
たとえば、L字に曲がった部分が多い排水管では、トイレットペーパーや流せるシートが詰まりやすいといえます。排水管は壁内や床下を通っているため視認できませんが、配管図などで確認してみましょう。
また、公共の下水道につながる排水管(排水桝の先)とトイレ・風呂の配置の関係によっても流れやすさが変わります。
トイレが手前にあれば風呂で使用する大量の水によって、排水が合流する場所の詰まりを押し流せます。一方、トイレが風呂よりも奥にある場合は、トイレの水だけで流す必要があるため、詰まりを解消しにくくなります。
流せるシートを詰まらせずに使う方法

トイレの流せるシートは、適切に使えば詰まりのリスクを低減できます。使う際のポイントを解説します。
複数枚を流さない
掃除で2枚以上の流せるシートを使用した場合は、1枚ずつ流すことが推奨されています。以下に、花王のトイレクイックルの注意喚起を紹介します。
花王のトイレクイックルの注意喚起
「トイレクイックル」シリーズのシートは、水の中に入れるとトイレットペーパーと同じ程度の速さでほぐれます。ただし、一度に大量のシートをトイレに流すと、トイレットペーパーと同様に、つまりの原因になることがあります。つまりを避けるため、1枚ずつ流してください。
シートをたくさん使用した時は、トイレに流さず、燃やせるごみとして出すことをおすすめします。
引用
一度に流す量が多いと、シート1枚あたりに当たる水流が分散され、十分にほぐれないケースがあります。一般的なトイレで流せることを検証されている商品でも、複数枚を1度に流すことが想定されていない可能性が高いため、流す量には注意しましょう。
また、流せるシートをたくさん使用した場合では、小分けに流しても溶け残ったものが蓄積して、排水管内を詰まらせる恐れがあります。3枚目以降は、燃えるゴミとして出すように心掛けましょう。
2~3回水を流す
トイレに流せるシートを捨てる際は、2〜3回水を流すのがおすすめです。数回流すことで、1度の洗浄では流れ切らなかったシートの繊維や汚れの排水管への滞留を防げます。
水量の少なさが詰まりの原因になりやすいため、特に節水トイレの場合は多めに水を流してあげると安心です。
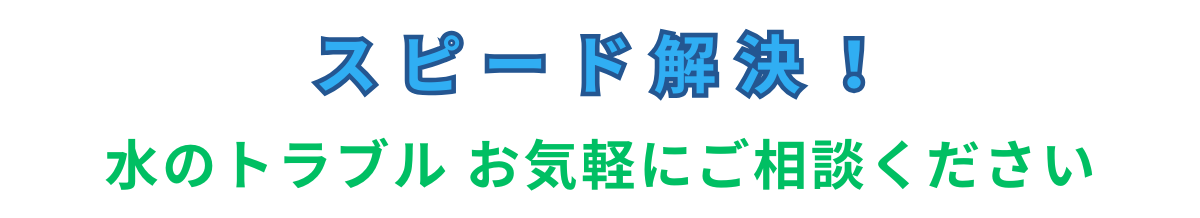
トイレの流せるシートの選び方

ここでは、詰まりにくいシートの選び方を3つ紹介します。
トイレットペーパーの基準に適うものを選ぶ
トイレに流せるシートのパッケージやメーカーの公式サイトで「JIS P4501」に適合しているかを確認しましょう。
「JIS P4501」はトイレットペーパーの規格です。基準を満たしている商品は、トイレットペーパーと同等のほぐれやすさを有していると考えられます。詰まりのリスクもおさえられます。
厚手で破れにくいものを選ぶ
JIS規格に適合していることが前提になりますが、厚手で破れにくいものをおすすめします。便器から床・壁まで1枚で掃除を完結できるものであれば、使用枚数の削減につながるからです。
一方、薄手のもの、破れやすいものは、結果的に複数枚を使用することになるため、小分けに流す手間がかかるほか、詰まるリスクも高くなります。
凹凸があるものを選ぶ
シート表目に凹凸(エンボス加工)があるかもチェックしましょう。凸凹がある方が汚れをしっかり絡め取ってくれるため、効率的に掃除できます。清掃性能が高い分、使用枚数を減らすことにもつながります。
流れるシートがトイレに詰まったときの対処法

流せるシートを流した後にトイレの水の流れに異変が生じた場合、シートの詰まりが原因の可能性があります。ここでは、流せるシートがトイレに詰まったときの対処法を解説します。
お湯を流す
まず試したいのが、お湯を流す方法です。50〜60度のお湯を用意し、便器に静かに注ぎます。お湯を注いだら約1時間放置し、その後水を流してみましょう。この方法は、便器の「せき」に詰まったシートをほぐすためのものです。
なお、熱湯を使用すると便器を損傷させる恐れがあるため、必ずぬるま湯を使うようにしてください。
スッポン(ラバーカップ)を使う
お湯で詰まりが解消しない場合は、スッポン(ラバーカップ)を使ってみましょう。
まずはトイレの水量を調節します。詰まりにより便器内の水が溢れそうなほど多ければ、バケツなどを使って水を汲み出します。水が少なければスッポンのカップ部分が水に浸かる程度まで水を追加してください。
水量を調節した後は、スッポンを便器の排水口に密着させ強くゆっくり押し込み、引っ張ります。何度か繰り返すことで、流せるシートによる詰まりを解消できる場合もあります。
トイレ用溶剤を使う
トイレ用のアルカリ性溶剤(パイプクリーナー等)など、市販のトイレ詰まり用の溶剤を使う手もあります。アルカリ性溶剤(は排水口や排水管詰まりの解消に効果的で、流せるシートが原因の詰まりの解消も期待できます。
アルカリ性溶剤には、ほかにキッチン用や浴室用などのタイプもありますが、トイレに使う場合は必ずトイレ用のものを選びましょう。専用のクリーナーでないと便器や配管にダメージを与える恐れがあります。
業者に依頼する
詰まりが解消しない場合や、水位が上がってきてしまう場合は、水道修理業者に依頼しましょう。無理に対処しようとすると、逆に詰まりを悪化させてしまう可能性もあります。また、壁内・床下の排水管の途中で詰まっているなど、個人での対応は難しいケースも考えられます。
トイレの水の流れに違和感を感じた際は、早めに業者に相談すると安心です。詰まりが軽度の段階で対処してもらえれば、時間も費用もおさえられます。
まとめ
流せるシートは、掃除後にそのままトイレに流せる便利なアイテムです。衛生的でゴミも減らせる一方、使い方やトイレの配管構造によっては詰まりの原因になることもあります。
使用する際は、JIS規格に適合した厚手で丈夫なシートを選ぶ、複数回に分けて流すなどに注意しましょう。
詰まってしまった場合、自分で対処する方法もありますが、改善しない場合は業者に相談した方が良いかもしれません。速やかに適切な対処をしてもらえます。
手軽に使えて衛生面でもメリットの多いトイレの流せるシートは、トイレ掃除の強い味方です。使い方に気をつけて、ぜひ日々のトイレ掃除に活用してください。