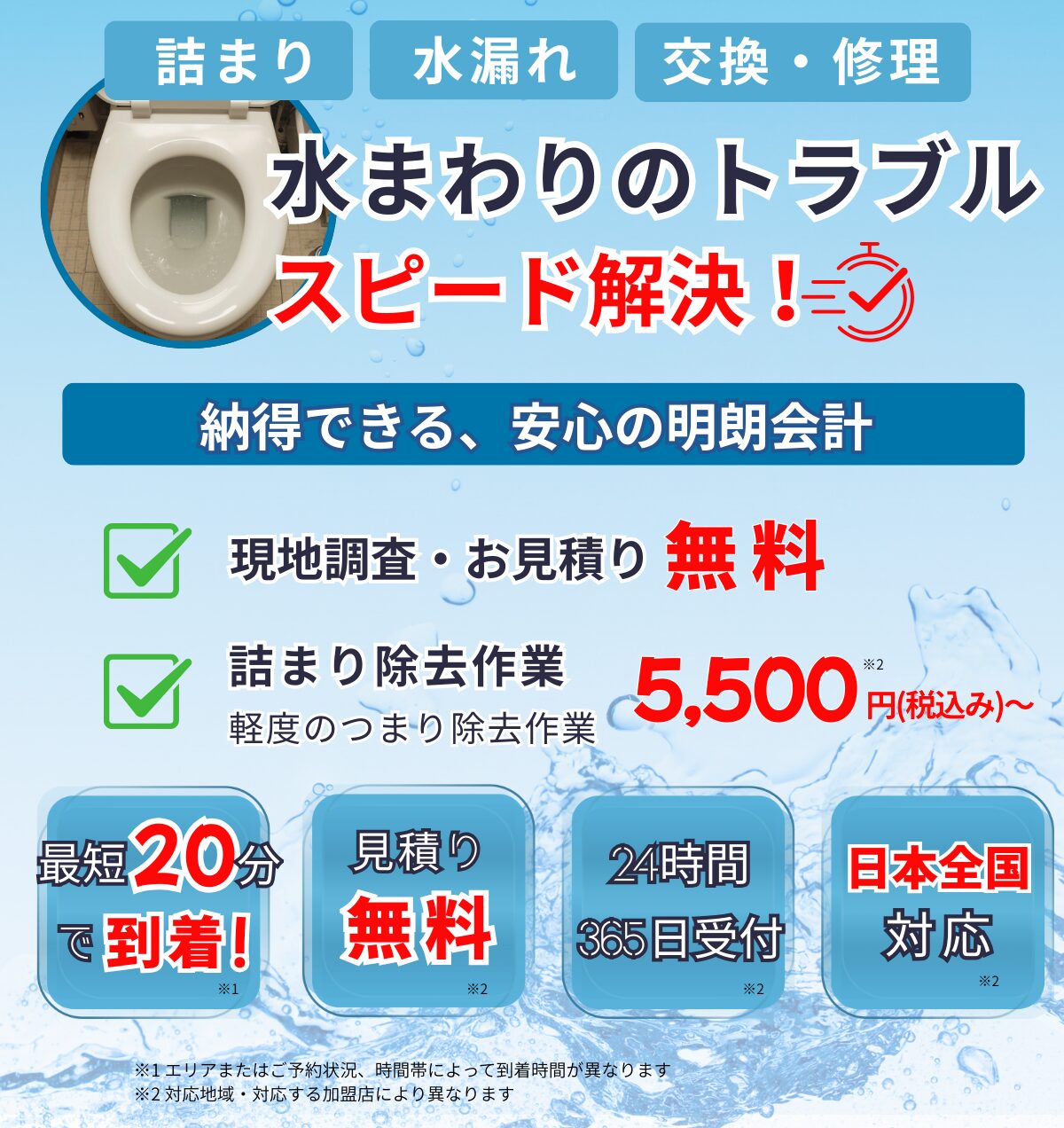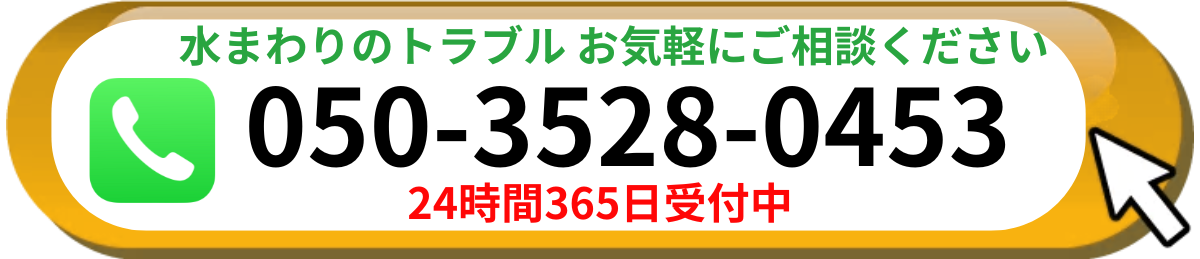「トイレの寿命は?」「何年で買い替えるの?」など、トイレは何年使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。トイレの耐用年数は、一般的には10〜15年と言われていますが、実際には部品の状態や使用頻度によって前後します。
本記事では、税務上の「法定耐用年数」と実際の「使用上の寿命」の違いをはじめ、トイレの耐用年数を具体的に解説します。買い替え時期の目安や、寿命が近づいているサインとして気をつけたい症状も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
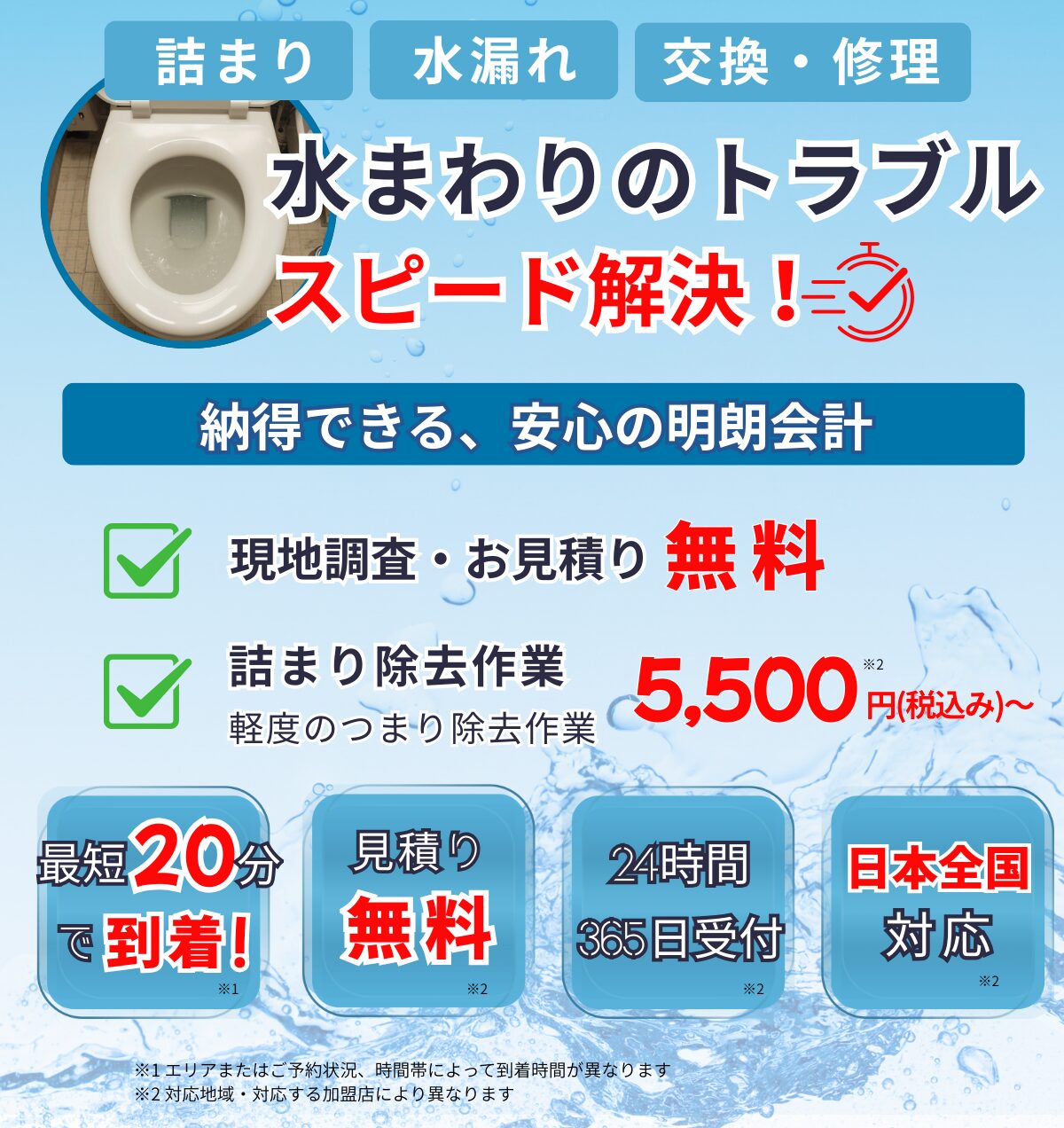
トイレの耐用年数とは?
トイレには耐用年数の目安があります。ここではトイレの耐用年数の目安と考え方を解説します。
トイレの「耐用年数」と「寿命」の考え方

トイレの「耐用年数」には、税法上の考え方である「法定耐用年数」と「実際の寿命」の2つの意味が含まれます。
トイレの法定耐用年数(減価償却)
トイレの「法定耐用年数」は15年と定められています。法定耐用年数は会計上の「減価償却」という考え方に基づくものです。
減価償却とは、建物や機械など長く使う資産の購入費用を「使う年数」に分けて少しずつ経費として計上し、利益を正しく計算するための会計ルールを指します。この「使う年数」は 「法定耐用年数」と呼ばれ、資産の種類ごとに 税法で定められた基準があります。
法定耐用年数を決める考え方は次のとおりです。
法定耐用年数を決める考え方
- その資産が通常どれくらい使用できるか
- 物理的な寿命や経済的価値の持続期間
- 過去の統計データ
こうした考え方をもとに、国税庁が法定耐用年数を示しています。トイレの便器・タンクなどが該当する住宅用衛生設備の法定耐用年数は15年です。
ただし、15年は税務上の評価にすぎないため、トイレ自体が15年で使えなくなるというわけではありません。
実際のトイレの耐用年数(寿命)
一般的に、トイレの寿命は10〜15年程度とされています。これは法定耐用年数とは異なり「実際に使えるかどうか」という観点から見た目安です。
便器の使用可能期間は100年以上ともいわれていますが、ウォシュレット(※)やパッキン、タンク内の部品の寿命は短く、10年で寿命を迎えることも少なくありません。。そのため、トイレ全体としての寿命は10〜15年とされています。
ただし、寿命はあくまで目安であり、使用頻度によっても変わります。10~15年経過していなくても、水漏れや洗浄力の低下、ニオイ残りなどが出てきた場合は修理や交換の検討が必要です。
このように、トイレの実際の寿命はパーツの状態や使用感から判断することになります。本記事ではこの「実用上の寿命」という観点から、トイレの耐用年数について詳しく解説していきます。
※TOTOの登録商標
トイレのパーツ別|耐用年数の目安
トイレは便器、便座・ウォシュレット、タンク、配管、パッキンなど、複数の部品で作られています。耐用年数はパーツごとに異なります。
| トイレのパーツ | 耐用年数(寿命) |
| 便器 | 陶器が割れない限り使用できる |
| 便座・ウォシュレット | 10年程度 |
| タンク | 陶器が割れない限り使用できる |
| タンク内の部品 | 10〜15年程度 |
| パッキン | 20年程度 |
| 配管 | 20年程度 |
便器とタンクはひびや傷ができない限り使用できます。耐用年数は100年以上とも言われていますが、黄ばみや汚れの落ちにくさが気になってきたら交換を検討しても良いかもしれません。
ウォシュレットの寿命は10年程度とされていますが、故障により数年で使用できなくなるケースもあります。
快適性や清潔面で気になる点がでてきたら、修理・交換を検討する時期といえるでしょう。
トイレのタイプ別|耐用年数の目安
トイレのタイプによっても耐用年数の目安は異なります。
| トイレのタイプ | 画像 | 耐用年数(寿命) |
| タンクレストイレ |
 |
便器・便座・タンクのいずれかに不具合が出るまで |
| 一体型タンク式トイレ |
 |
便器・便座・タンクのいずれかに不具合が出るまで |
| 分離型タンク式トイレ |
 |
パーツごとに判断できる |
タンクレストイレは水を溜めるタンクがないトイレ、一体型タンク式トイレは便器・便座・タンクが一体化したトイレです。
タンクレストイレと一体型タンク式トイレは構造上、基本的に「便座だけの交換」や「ウォシュレットだけの交換」ができません。そのため、不具合が出た際はトイレ全体を丸ごと取り替える必要があります。寿命が短いパーツに合わせて交換することになるでしょう。
分離型タンク式トイレは、便器・便座・タンクを組み合わせたトイレです。それぞれのパーツが独立しているため、壊れたパーツだけを交換し、問題のない部品はそのまま使い続けることが可能です。
先述の「トイレのパーツ別|耐用年数の目安」を参考に、各パーツをメンテナンスしていきましょう。
トイレの買い替え時期は?気をつけたい症状の具体例

トイレの耐用年数・寿命はあくまでも目安です。経年劣化や故障の兆候が現れたら、耐用年数を迎えていなくても修理や買い替えを検討した方がよいかもしれません。ここでは、寿命が近いトイレの具体的な症状を解説します。
トイレの寿命が近づいた時にみられる症状を解説します。
水漏れやするようになった
配管やタンク周辺のパッキンが劣化すると、水漏れを起こすことがあります。トイレの床が濡れているなど水漏れがみられる場合は、早めに修理か交換を検討しましょう。長期間放置すると床材が傷んだり、水漏れによる被害が広がったりする可能性もあります。
パッキンの交換で改善するケースもあるため、水漏れに気づいた段階で水まわり修理の専門業者に相談するのがおすすめです。
ニオイや汚れが気になるようになった
「掃除をしているのにトイレのニオイが気になる」「汚れが落ちにくくなった」という場合は、便器の交換のタイミングです。
便器の表面には汚れの付着を抑えるコーティングが施されています。経年劣化によってコーティングが剥がれると、汚れがつきやすくなり、悪臭の原因となることがあるため注意が必要です。また、便器の劣化も進むため、買い替えを検討しましょう。
水を流した時に異音がする
水を流した際に便器やタンクから異音がする場合は、排水管の詰まりやタンク内の部品の故障が疑われます。トイレが使用できなくなる可能性もあるため、早めに業者に点検を依頼するのがおすすめです。必要に応じて、修理や買い替えを検討しましょう。
ウォシュレット(温水洗浄便座)の故障が頻発している
ウォシュレットに次のような症状が頻発している場合は、ウォシュレットの寿命が近づいている可能性があります。
ウォシュレットの主な不具合
- ボタンを押しても作動しない
- 温水が出ない
- ノズルが出ない
- 便座の温度調整ができない
- 水漏れしている
ウォシュレットは電化製品です。電子機器の寿命は短く、およそ10年前後で故障のリスクが高まるといわれています。10年経つ前でも、不具合が繰り返し起きるようであれば買い替えを検討するタイミングです。
なお、分離型タンク式トイレの場合は、ウォシュレットだけを交換できます。一方、タンクレストイレや一体型タンク式トイレのウォシュレットが故障した際は、基本的にトイレ全体の買い替えが必要です。
水の流れが悪くなった
水の流れが悪くなった場合は要注意です。たとえば次のような症状が出た場合は、配管の詰まりやタンク内のパーツの故障が原因かもしれません。
注意したいトイレの不具合
- 水が流れない
- タンクに水は溜まっているのに流れが悪い
- 流した後もタンク内の水位が高い
- 水の流れる勢いが弱い(タンクレスの場合)
さまざまな要因が考えられるため、買い替えの必要性を含め業者に相談するのがおすすめです。
手洗い器に不具合がある
手洗い器の水がなかなか止まらない、水量の調整がうまくできないなどの場合は、手洗い器の部品の不具合が考えられます。
パッキンなど内部部品の交換で改善するケースもあります。ただし手洗い器付きタンクで、部分的な修理が難しい場合はタンク全体(一体型の場合はトイレ全体)の交換が必要です。
部品交換を何度も繰り返している
部品交換を繰り返せば、修理費用もかさんでいきます。また、部品がすでに製造終了しているケースもあり、修理自体が難しい場合もあります。
今後のランニング費用やメンテナンスの手間、利便性を考えると、新しいトイレに買い替えた方が良いかもしれません。
節水機能など最新機能に魅力を感じるようになった
近年のトイレは節水性や清掃性が大きく進化しているため、ランニングコストや手間を考えると買い替えた方がお得ということも少なくありません。
たとえば、以前は洗浄1回あたり10リットルほどの水が必要でしたが、今は4~6リットルほどの水で流せるトイレも登場しています。また、使用後に自動で水を流してくれる「自動洗浄機能」や掃除がしやすい「フチなし設計の便器」など、高い利便性も魅力です。
ランニングコストや使い勝手を重視したい場合は、欲しい機能が搭載されたトイレへの買い替えを検討してみましょう。
トイレの耐用年数についてのQ&A

トイレの耐用年数についてよくある疑問を解説します。
耐用年数を超えたトイレは必ず交換すべき?
耐用年数を超えたからといって、必ずしも交換が必要になるわけではありません。特に問題がなければ、そのまま使い続けられます。ただし、劣化や故障など不具合がでた際は早めに対処しましょう。突然トイレが壊れて使えなくなる可能性があります。
不具合がある場合は、症状に応じて修理か交換を選べます。それぞれのメリットとデメリットは次のとおりです。
| 対応区分 | メリット | デメリット |
| 修理する場合 | 費用をおさえられる | さらなる修理が必要になる可能性がある 修理費用が高額になる場合がある |
| 交換する場合 | 欲しい機能を備えたトイレにできる 長期的に安心して使える |
費用がかかる 工事の手間がかかる |
修理の場合、今後別の箇所の故障が発生する可能性や、修理内容によっては高額な費用がかかるケースもあります。ただし、基本的には交換よりも費用をおさえられるでしょう。短時間で対処できる場合もあるため、気になる症状が出たらまずは業者に相談してみるのがおすすめです。
交換する場合、初期費用はかかりますが、使用時の安心感や利便性の向上が期待できます。節水性能が高いトイレであれば、水道代をおさえることにもつながるでしょう。
修理か交換かを選べるのは、基本的に分離型タンク式トイレのみです。タンクレストイレと一体型タンク式トイレはパーツごとの修理が難しいため、トイレ全体の交換になる可能性があります。
トイレの買い替えにかかる費用はどのくらい?
トイレの交換の際は、トイレ本体の料金に加えて工事費もかかります。トイレのタイプ別の相場は次のとおりです。
| トイレのタイプ | 画像 | 費用 (本体+工事費) |
| タンクレストイレ |
 |
20〜30万円程度 |
| 一体型タンク式トイレ |
 |
20〜30万円程度 |
| 分離型タンク式トイレ |
 |
5〜15万円程度 |
分離型タンク式トイレが一番安価に導入できる傾向があります。タンクレストイレや一体型タンク式トイレはスタイリッシュでおしゃれなデザインが多い一方、導入費用は高額になりがちです。
トイレの買い替えで活用できる補助金はある?
交換するトイレのタイプやリフォームの目的によって、補助金を利用できる場合があります。たとえば次のような補助金があります。
| 目的 | 補助金 |
| 節水トイレへの交換 | 子育てグリーン住宅支援事業 地方自治体の補助金 |
| トイレのバリアフリー化 | 介護保険 地方自治体の補助金 |
補助金の種類や申請条件などは変わる可能性があります。必ず公式サイトで詳細を確認してください。
トイレの設置で使える補助金に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
トイレの耐用年数は10〜15年ほどと言われていますが、パーツの劣化状況や使用頻度などで前後します。パーツごとに寿命は異なり、便器の耐用年数は長い一方、ウォシュレットは数年から10年ほどで交換が必要になることもあります。
使用中に異音や水漏れ、ニオイなど気になる症状が出てきたら、耐用年数前であっても修理や買い替えを検討するタイミングです。対処が遅れるとさらなるトラブルが起きたり、故障によりトイレが使えなくなったりするケースもあります。
安心してトイレを使うためにも、早めに専門業者に相談して対応を考えましょう。